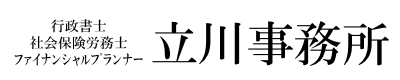終活
成年後見制度(法定後見、任意後見)、見守り契約・死後事務委任契約
認知症等で本人の判断能力が不十分な疑いがあると、夫婦や親子の関係にあることを証明しても、本人のために必要なことだと説明しても、「後見人を付けてもらわないと…」と預金の引き出し等の手続きを断られることがあります。
不正な目的を持っていない家族は、なぜ後見人がいなければ本人のための行為が出来ないのかと違和感を感じるところですが、そのような現状を理解したうえで対応を考えざるを得ません。
また、身近に頼れる人がいない場合など、どのように後見人等を頼ればいいのか、その仕組みを予め知っておきたいという方もいるでしょう。
自分で出来ないことを誰にどのように任せるかは、終活においても特に重要な問題です。
既に判断能力が不十分な場合
認知症、知的障害、精神障害などにより本人の判断能力が十分でないと、法律行為(売買契約、医療契約、要介護認定申請等)を適切に行えず、生活に支障が生じることがあります。
本人の判断能力の程度によってその権限の範囲は異なりますが、家庭裁判所が選任した後見人等(後見人・保佐人・補助人)が、代理人として契約したり、本人に不利な契約を取消したりして、本人の生活を支えるのが「法定後見制度」です。
なお、実際に介護等のお世話をすることは「事実行為」といい、必要な事実行為がなされるように契約を結ぶこと等(法律行為)が後見人等の役割です。
この法定後見制度は、本人の判断能力が衰えてから、家族等が裁判所に申し立てることによって始まる制度であり、後見人を自分で選べない難点があります。(家族等が推薦することは可能だが、裁判所は別の人を選ぶことができる。)
これに対して、任意後見制度は、本人の判断能力に問題がないうちに、誰に何を委ねるか(任意後見人と代理権の範囲)を契約で決めておき、本人の判断能力が衰えたら家庭裁判所に申し立てて、その契約相手が任意後見人として本人の生活を支える制度です。
法定後見制度と任意後見制度を併せて「成年後見制度」と呼びます。
後見人による横領事件の発生や後見人報酬の負担感等多くの問題点が指摘されていますが、家庭裁判所が後見人等を監督してくれること、今後は本人や後見人等を支えるための地域連携ネットワークの整備が進む予定となっていることなどから、今後も重要な選択肢であり続けるものと思われます。
判断能力に問題がない場合
成年後見制度は「判断能力」がポイントになっており、身体的な不自由さを理由にして利用することはできません。
もちろん、判断能力の衰えていない人が代理権を与える契約を結ぶことは可能であり、「見守り契約」「任意代理契約」「事務委任契約」などと呼ばれています。
成年後見制度であれば、本人の判断能力が十分でないことを前提に、後見人等が本人のためにならないことをしない様な仕組み(裁判所による監督等)が整えられていますが、本人の判断能力に問題がないことを前提とするこれらの契約については、契約相手(自分で選んだ代理人)の不正防止に不安があります。
また、成年後見制度は「身上監護」と「財産管理」を行うものですが、本人の判断能力に問題がない場合には、財産管理契約、家族信託契約と呼ばれる、財産管理のみを委ねる契約を結ぶことも可能です。法定後見制度と異なり、資産運用の方法も特に制限されません。
本人の判断能力が衰えた後に裁判所が関与し始める(本人のリスク選好を確認できない)法定後見制度では、元本保証のない資産運用を後見人が始めることは認められないようです。
- 信託(家族信託、民事信託)
- 成年後見制度と併せて検討されることが多くなってきた「家族信託」の仕組みは、非常に自由度が高く、様々なニーズに合わせてカスタマイズ出来るため注目されています。
ただ、「信託」を専門に扱う信託銀行が数千万円以上を管理する資産家しか相手にしてくれないのと比較すると遥かに身近な「家族信託」ですが、基本的にはオーダーメイドの契約になるため、少なくとも数十万円の費用が掛かります。
財産の名義を事前に書き換えておくため、本人(委託者)の判断能力に問題が生じた場合にも、その財産管理に不都合が生じ難くなるのは間違いありません。
例えば、大家さんとしてアパート経営をしているような場合、賃借人・管理会社・修理業者・銀行等との法律的なやり取りが出来なくなった際に本人の生活費にも支障が生じるようなら、検討してみた方が良いでしょう。
一方で、銀行預金や自宅不動産しか管理すべき財産がない場合にまで、信託の仕組みを用いるのは大袈裟過ぎるように思います。
預金の引き出し程度なら、それぞれの金融機関で用意された代理人登録制度などを活用すれば当面の不安は解消されるということも多いでしょう。機動性・柔軟性には欠けますが、どうにもならない状況になってから成年後見制度を利用する道は、常に残されているのです。
本人の判断能力に問題が生じた後、代理人カードで取引を続けることがルール違反になる様な可能性は否定できませんが、信託契約で名義を移しても良いと思う程の信頼関係があるのなら、その程度の違反には目を瞑るという判断も、実務的にはあり得ると思います。
国家資格者として、堂々と応援することは難しいですが、一般市民にとっては、法的な正しさよりも目の前の生活の方が大切なのは当然だと思います。
判断能力に問題がない場合(死後のこと)
特別な事情がなければ、本人が死亡すると代理権も消滅します。
(代理人のした行為の効果を本人に帰属させるのが「代理」であり、死者(この世にいない人)に権利や義務を帰属させるのは無理があるため。同じ理由で、死後に代理権を与えることはできない。)
しかし、見守り契約等を結ぶ人は、頼れる身内が近くにいない場合が多く、死後の身辺整理まで依頼したいというニーズがあるため、生きている間の代理権(見守り契約等)を前提として「死後事務委任契約」等を結ぶこともあります。
死後事務の内容は、以下のようなものです。
・親族、知人への連絡
・葬儀、埋葬の手配
・病院、施設、アパート等の片付け
・料金の支払い
・役所の手続き
住んでいる地域によっては、市役所や社会福祉協議会等が類似のサービスを用意している場合があります。
このような、常識的に考えて誰かがやらなければ困ることを委ねるのは可能ですが、残ったお金(遺産)を寄付するといった内容は、相続人の財産権の侵害等の問題が生じ得るため、遺言や死因贈与契約等として別途整理する必要があります。また、実際の手続きについても、相続等の法律に明るい人でなければ、本人の最期の意思を実現できないおそれがあります。
なお、全く身寄りのない(相続人、引き受けてくれる親族・知人等がいない)方については、法定後見制度を利用している場合は後見人等が死後事務まで行うことができます。
また、ある程度の遺産があれば、死後事務契約や後見制度の利用がなくても、相続財産管理人が選ばれて必要な死後事務や清算(相続)が行われますが、そうでない場合は市町村が火葬等を行う様な対応になります。
連絡すべき相手を調べる必要性から、警察官・自治体職員等が故人の持ち物を調べたりすることもありますが、料金支払い等は原則としてできません。(世間の常識としては問題なさそうに思えても、施設や病院等の一部の債権者に故人のお金(厳密には、既に相続人の財産となったもの)を支払うことは、法律等で定められた手続きを抜きにして行うべきではないため。)
「自分の死後のことにどこまで責任を持つ必要があるのか」については、考え方に個人差が生じるところですが、「死んだ後も人に迷惑を掛けたくない」と思う方や、「死んだ後のことにもあれこれこだわりたい」と思う方は、成年後見制度等について勉強して、誰にどのように任せるのかを考えてみる必要があります。